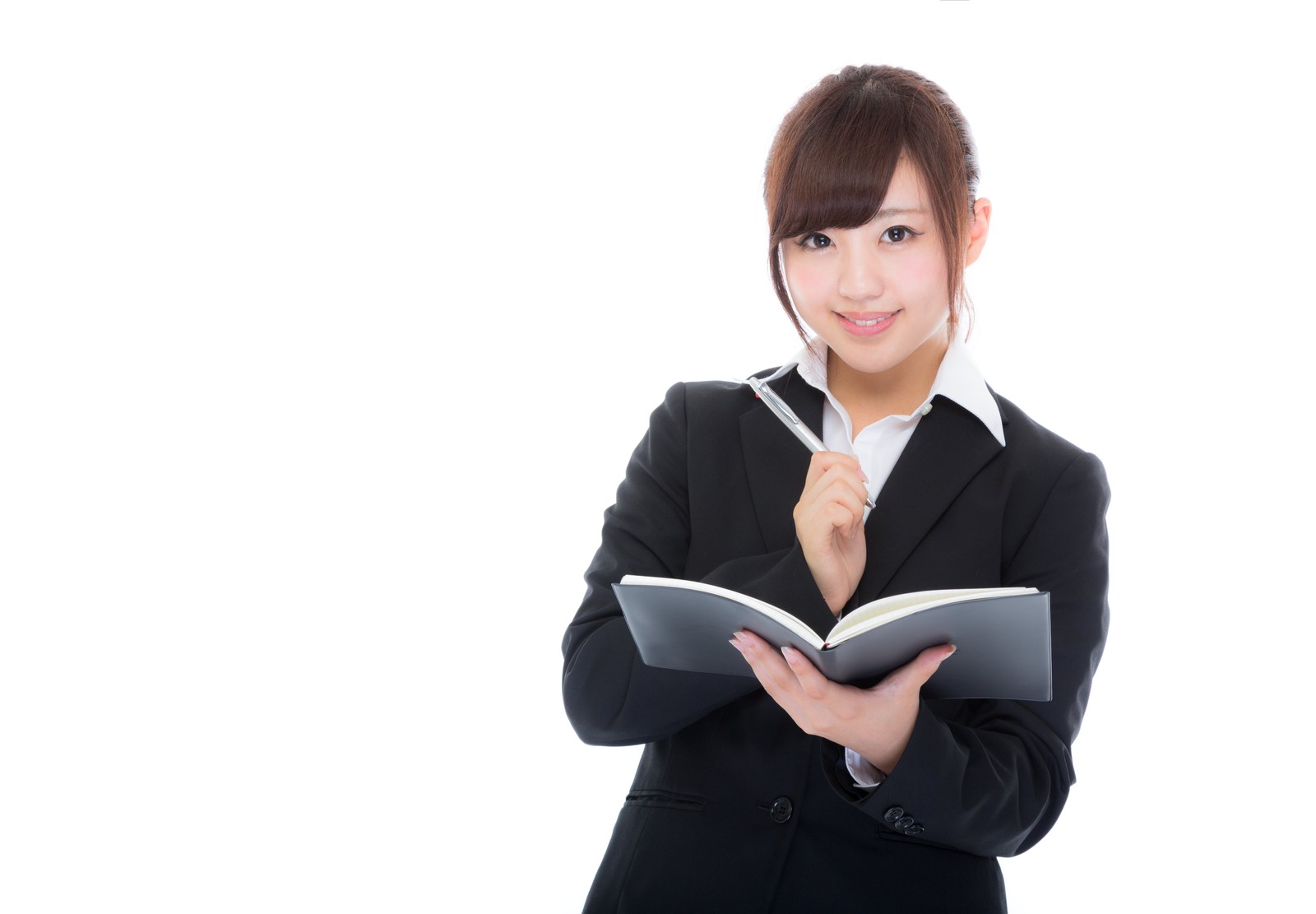「最近、なんだか疲れがとれない…」「肩こりや目の奥の痛みが慢性化している…」
もしかすると、その不調の原因はビタミンB1が不足しているからかもしれません。
ビタミンB1は、私たちの健康に不可欠な栄養素でありながら、現代の食生活では不足しやすい「隠れ不足ビタミン」の一つとも言えます。
この記事では、ビタミンB1の基本的な知識から、具体的な健康効果、不足した時に起こる深刻な症状、そして賢い摂取方法まで解説していきたいと思います。
この記事を読めば、ビタミンB1の重要性を再認識し、日々の健康管理に役立てることができるはずです。
ビタミンB1の基本|「エネルギー代謝」のキープレイヤー
ビタミンB1は、水に溶ける水溶性ビタミンの一つで、「チアミン」とも呼ばれます。
水溶性であるので、体内に貯めておくことができず、必要量を超えた分は尿として排出されます。
なので、毎日継続的に摂取することが非常に重要です。
(1) ビタミンB1の最も重要な役割|糖質をエネルギーに変える
私たちの身体は、食事から摂取した糖質を主要なエネルギー源としています。
しかし、糖質はそのままではエネルギーにすることができません。
ここで活躍するのがビタミンB1です。
ビタミンB1は、糖質がブドウ糖に分解され、さらに細胞内でエネルギー(ATP)に変わる複雑な代謝プロセスにおいて、補酵素として働きます。
この補酵素がなければ、糖質の代謝はスムーズに進まず、エネルギーを効率よく生み出すことができません。
(2) 脳と神経機能の維持にも不可欠
脳は、多くのエネルギーを消費します。
そのエネルギー源は、ほぼブドウ糖に依存しています。
前述の通り、ビタミンB1はブドウ糖の代謝に不可欠なため、脳の活動を正常に保つのに極めて重要な役割を担っています。
ビタミンB1が不足すると、脳へのエネルギー供給が滞り、集中力の低下や記憶力の減退、イライラなどの精神的な不調につながることがあります。
また、末梢神経や中枢神経の働きを正常に保つためにもビタミンB1は必要になります。
これが不足すると、手足のしびれやむくみといった神経系の症状が現れることがあります。
知らずのうちに陥る「隠れビタミンB1不足」
現代の食生活は、ビタミンB1が不足しやすい環境にあります。
特に、以下の食習慣を持つ方は注意が必要です。
- インスタント食品や加工食品、レトルト食品を頻繁に食べる
これらの食品は、手軽で便利ですが、製造過程でビタミンB1が失われていることが多く、また、糖質が主体のものが多いため、ビタミンB1の消費を加速させてしまいます。 - 白米や白いパン、うどんなど、精製された穀物を主食にしている
米や小麦は、精製される過程でビタミンB1が多く含まれる胚芽や糠、外皮が取り除かれてしまいます。 - 清涼飲料水や甘いお菓子、ジュースをよく飲む
砂糖や果糖が多く含まれる食品は、体内で代謝するためにビタミンB1を大量に消費します。 - アルコールの摂取量が多い
アルコールの分解には、ビタミンB1が大量に使われます。
また、アルコールには利尿作用があるため、ビタミンB1が体外に排出されやすくなります。
これらの習慣は、自覚がないままビタミンB1不足を招き、「なんとなく調子が悪い」という状態を作り出します。
ビタミンB1不足が引き起こす深刻な病気と症状

ビタミンB1の不足が慢性化すると、単なる疲労感だけでなく、様々な身体的・精神的な不調へと発展する可能性があります。
(1) 初期症状|疲労感や精神的な不安定さ
ビタミンB1不足の初期症状として、最も自覚しやすいのは疲労感です。
エネルギーが効率よく作られないため、すぐにだるさを感じたり、集中力が続かなくなったりします。
また、神経系の機能が低下することで、イライラしたり、気分が落ち込んだりすることもあります。
(2) 中期症状|神経系の不調と消化器系の問題
不足が進行すると、手足のしびれやむくみ、筋肉の疲労感、消化不良、食欲不振などが現れます。
これは、末梢神経や消化器系の働きが弱まるためです。
肩や首のこりがひどくなる方も少なくありません。
(3) 欠乏症|脚気(かっけ)とウェルニッケ・コルサコフ症候群
ビタミンB1の欠乏がさらに進むと、脚気(かっけ)やウェルニッケ・コルサコフ症候群という重篤な病気を引き起こす可能性があります。
- 脚気
心不全や末梢神経障害を主症状とする病気です。
江戸時代から明治時代にかけて、白米中心の食生活によって多くの患者が発生しました。
現代では稀ですが、偏った食生活を送る人やアルコール依存症の人に見られることがあります。 - ウェルニッケ・コルサコフ症候群
脳のブドウ糖代謝が滞ることで引き起こされる神経精神障害です。
重度の記憶障害や目の動きの異常、歩行困難などを引き起こします。
これらの病気は、ビタミンB1の欠乏が原因であることがわかっています。
ビタミンB1を効率よく摂取するための食べ物とレシピ
ビタミンB1は、日々の食事から意識して摂ることで、不足を予防できます。

(1) ビタミンB1が豊富な食材リスト
ビタミンB1は、意外な食材に豊富に含まれています。
| 食材グループ | 主な食品例 |
| 肉類 | 豚肉(ヒレ、もも、ロースなど)、レバー |
| 穀類 | 玄米、胚芽米、雑穀米、全粒粉パン、そば |
| 豆類 | 大豆、枝豆、納豆 |
| 種実類 | ごま、ピーナッツ、カシューナッツ |
| その他 | 卵、うなぎ、まいたけ、たらこ |
中でも豚肉は、ビタミンB1の含有量が非常に多く、効率よく摂取できます。
(2) 吸収率を高める賢い組み合わせ
ビタミンB1は、ある成分と一緒に摂取することで、吸収率を格段に高めることができます。
- アリシンを含む食品と組み合わせる
にんにく、玉ねぎ、ニラなどの匂い成分「アリシン」は、ビタミンB1と結びついて「アリチアミン」という物質に変化します。
アリチアミンは、ビタミンB1よりも体内に長くとどまり、効率よく利用されるという特徴があります。
豚肉の生姜焼きにたっぷり玉ねぎを加える、豚肉とニラの炒め物にするなど、積極的に組み合わせてみましょう。 - 水に溶けやすい特性を活かす
ビタミンB1は水溶性のため、煮物やスープにすると水に溶け出してしまいます。
しかし、汁ごといただくことで、溶け出したビタミンB1も無駄なく摂取できます。 - 加熱しすぎない
ビタミンB1は熱に弱い性質を持っています。
調理する際は、短時間でさっと加熱する炒め物などがおすすめです。
(3) ビタミンB1をたっぷり摂れる簡単レシピ
【レシピ1】豚肉と玉ねぎのスタミナ生姜焼き
豚肉と玉ねぎに、すりおろし生姜、醤油、みりんを加えて炒めるだけ。ご飯がすすむ定番料理です。
【レシピ2】玄米とごまの混ぜご飯
いつもの白米を玄米に変え、炊きあがったご飯にごまや枝豆、ひじきの煮物などを混ぜるだけ。手軽にビタミンB1と食物繊維をプラスできます。
【レシピ3】豚汁
肉、ごぼう、にんじん、里芋、きのこなど、ビタミンB1を含む食材をたっぷり入れることで、栄養満点の汁物になります。
汁ごといただくことで、溶け出した栄養素も逃しません。
サプリメントは必要?過剰摂取の心配は?
食事から摂取するのが理想ですが、バランスの取れた食事が難しい場合、サプリメントを利用するのも一つの選択肢になります。
ビタミンB1は水溶性のため、体内に蓄積されにくく、過剰摂取による健康被害の心配はほとんどないとされています。
ただし、ビタミンB群は単体ではなく、お互いに助け合って働くことが多いので、できればB群全体をバランスよく含むサプリメントを選ぶのがおすすめです。
サプリメントはあくまで食事の補助として活用し、まずは日々の食生活からビタミンB1を意識して摂ることを心がけましょう。
サプリメントをメインに考えないようにしましょう。
まとめ
ビタミンB1は、日々の活動に必要なエネルギーを生み出す上で欠かせない栄養素です。
慢性的な疲労や身体の不調を感じる方は、ビタミンB1の摂取量が不足していないか、一度食生活を見直してみてはいかがでしょうか。
この記事のまとめ
- ビタミンB1は、糖質をエネルギーに変える重要な役割を担っている。
- 不足すると、疲労、肩こり、集中力低下、食欲不振などの不調につながる。
- 豚肉、玄米、大豆、ごまなどに豊富に含まれている。
- にんにくや玉ねぎと一緒に摂ると吸収率が大幅にアップする。
- 過剰摂取の心配はほとんどないため、食事とサプリメントを上手に活用することが大切。