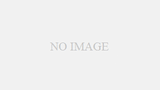クエン酸といえば、「疲労回復」や「ダイエット」に良いイメージを持つ方が多いのではないでしょうか。
では、その効果には科学的な根拠(エビデンス)が十分にあるのでしょうか?
本記事では、エネルギー代謝の仕組みをひも解きながら、クエン酸の効果について解説していきたいと思います。
クエン酸とは?基礎知識を解説!
私たちの身体は、食事で摂った糖質、脂質、タンパク質を分解し、最終的にATP(アデノシン三リン酸)という物質を作ることでエネルギーを得ています。
このATPがADP(アデノシン二リン酸)に変わる際に、エネルギーが発生しています。
エネルギー生成の鍵「クエン酸回路」
栄養素がATPを生成する過程の一つに、「クエン酸回路(TCA回路、クレブス回路とも呼ばれる)」があります。
食事で摂取した糖質や脂質などの栄養素が代謝され、このクエン酸回路に入ります。
回路の最初で生成される物質こそがクエン酸です。
クエン酸はさらに代謝を続け、この複雑な化学変化の過程でATP(エネルギー)が大量に生み出されます。
つまり、クエン酸は体内でエネルギーを生み出す代謝プロセスの重要な中間生成物になります。
【ダイエット効果】クエン酸を摂ればやせる?
「クエン酸を摂ることでクエン酸回路が活性化し、エネルギー代謝がアップしてやせる」といったクエン酸ダイエットの説を耳にすることがあります。
ですが、この説には信頼できるデータ(エビデンス)があるわけではないようです。
「何かを摂るだけでやせる」という特効薬は存在しません。
もし確実な効果があれば、それは「薬」として扱われるはずです。
世の中の多くのダイエット法には、科学的根拠がないものも多く、安易に信じるのは危険と言えます。
科学的根拠とは?
私たちが「信頼できるデータ」と呼ぶのは、プラセボ効果(思い込みによる効果)や主観(バイアス)を取り除き、統計的に信頼できる人数で研究され、効果が証明されたものです。
特に、エビデンスの信頼度が最も高いのは、RCT(二重盲検比較試験)という手法を用いた研究報告です。
一つの論文で効果が証明されても、それはあくまで「一つの研究結果」に過ぎません。
多数の研究論文を分析するメタ分析で効果が認められてこそ、強いエビデンスとなります。
むしろ逆効果の可能性も?
エネルギー生成の過程を考えると、クエン酸の過剰摂取はダイエットに逆効果になる可能性も考えられます。
栄養素(糖質・脂質など)はクエン酸回路に入ってクエン酸に変化し、さらに代謝されます。
代謝の中間生成物であるクエン酸を外から摂ってしまうと、本来、体内に蓄積している糖質や脂質がクエン酸回路に入るのを妨げてしまうかもしれません
そうなってしまえば、本来エネルギーとして使われるはずだった体内の栄養素が使われにくくなり、結果として脂肪として蓄積されやすくなるリスクが考えられるのです。
【疲労回復効果】クエン酸は疲れに効くのか?
クエン酸は、運動後の疲労回復に良いとしてアスリートにも愛用されていますが、残念ながら、疲労回復に関しても十分な信頼できる科学的データは不足しています。
「飲んで元気になった気がする」という感覚は、プラセボ効果かもしれません。
プラセボ効果とは、効果がないものでも「効く」と思って摂取することで、実際に体調が改善したり、疲労感が軽減されたりする現象です。
これは科学的に実証されており、心理状態が身体に影響を及ぼすことを示しています。
もちろん、プラセボ効果でも気分が良くなるのであれば、良いと思いますが、しっかりとした根拠がない以上、プラセボ効果以上の「確実な効果」をクエン酸に期待することは難しいです。
まとめ
- クエン酸は、体内でエネルギー(ATP)を生み出すクエン酸回路の代謝産物であり、エネルギー生成に不可欠な物質です。
- クエン酸の「ダイエット効果」について、信頼できる科学的なエビデンスはありません。
逆に代謝を妨げるリスクも考えられます。 - クエン酸の「疲労回復効果」についても、十分なエビデンスはありません。
感じられる効果はプラセボ効果の可能性があります。
健康維持やダイエットは、特定のサプリメントに頼るのではなく、バランスの取れた食事と適度な運動という基本的な生活習慣の見直しが最も大切だと思います。